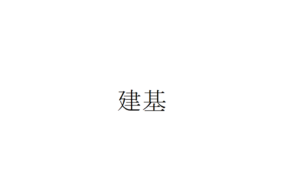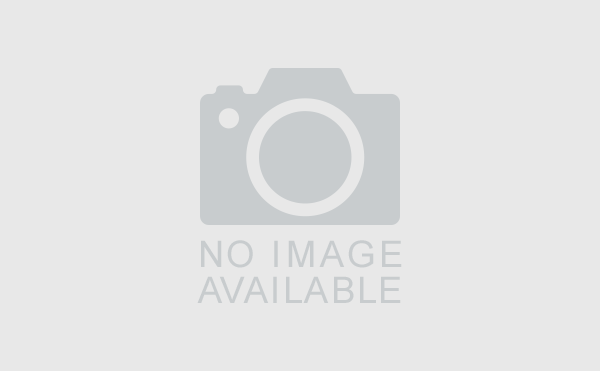宅建で出題され得る計算問題3 報酬額
宅建士試験は現在のところ電卓持込不可です
2024年7月1日報酬額告示により、空家等に係る報酬額が変更されました。・低廉な空家等の売買の媒介:30万+消費税
・長期の空家等の賃貸借媒介:大雑把に通常の2倍
低廉な空家等とは、800万以下の宅地または建物を言い、使用の状態を問わない(2025/1/1解釈・運用43頁)ので、
事実上800万以下の物件の売買媒介報酬は全て30万+消費税ということです。
一方、長期の空家等については、居住用・事業用を問わず1年超で使用者がいない建物・マンションの空室、
または今後使用の見込が無いものなどです(同解釈・運用44頁)。後者の例として、一般承継により不動産を取得したが
相続人も当該物件に住まないような場合を挙げてます。ありがちでしょう。
但し入居募集をしている集合住宅は長期の空家等に関する特例からは除外されます。
私はここも2024年度試験に出そうだと考えてましたが、出題されませんでした。改定が7/1なので、
すでに試験問題の大枠は作られていたということでしょうか。あくまでも想像です。
今年度は出題確率高めでしょう。
不動産登記法上においても空家等に関する問題が増加しているようです。
所有者不明ということです。
このような経緯から、不動産を相続したらきちんと登記しなさいと、罰則付きになりました。(不動産登記法76の2、同164)
また、来年、所有者の登記上の氏名・住所変更を怠った場合にも罰則が課されるようになります。(同2026/4/1施行分76の5、同164-2)
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策法」)もあります。
記憶によると、空家対策法で特定空家等不良な空家認定されると、固定資産税上の小規模宅地の特例などが効かなくなるようです。
なお、管理不全不動産及び所有者不明不動産に関する管理命令の条項が2年ほど前に新施行されてます(民264の2~264-14)。
空家等の肩身、せまっ。
本日は3つも投稿しました。通常の勉強法より、こうして発表するほうが、いい加減な内容にできず、より勉強になります。
大学ですと論文なんかがありましたね。そういう事です。
なお、最近宅建業法違反で挙げられた方がいるようですが、容疑は宅建業法違反らしいです。MSM経由なので、自分で確かめたわけではないので
あくまでも”らしい”です。噂の類です。宅建業の免許を取ってないのにこれを業として行ったという設定です。フィクションかノンフィクションであるかは 現在不明です。
法律の勉強・仕事をしている者が”噂”の類に左右されるわけにはいきません。知性や品格にかかわります。
MSMは裁判官でも何でもありません。
そもそも、”パクられた”時点では推定無罪です。
その上で、架空の話題として述べますと、
宅建業法に言う宅建業とは(宅建業法2-2)
・宅地建物の売買・交換
・宅地建物の売買・交換・賃貸借の代理か媒介
上記各号を業として行う事
“又は”と”若しくは”が連続しているせいで、読みにくい条項になってます。
業の構成要件としては、
1.不定多数に
2.反復継続して行う
と解釈して間違いないです。
分譲の売買等も当然”業”です。
宅建業免許も無いのに軽い気持ちで不動産のネット転売をやってるとパクられる可能性があるという事です。
名板貸しも同様に最高クラスの罰則があります。