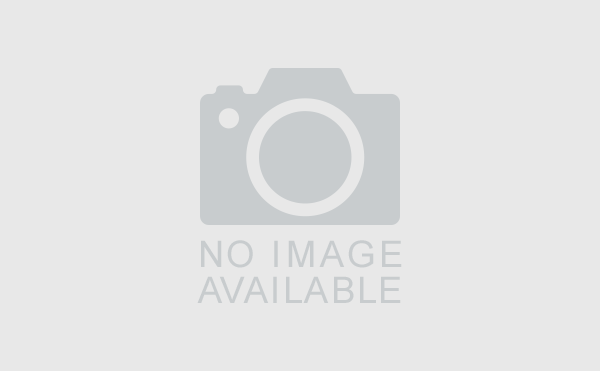塩トマト 塩メロン 導電率
塩トマトの糖度が上がる原理は以下の通りと記憶してます。
土壌の塩分濃度が濃いため、根からH2O及びイオンを吸収しにくい。
これは、果実肥大期において、与える水分を絞った状態に等しい。
少なくともトマトの場合、1果あたりの総糖量は概ね決まっているため、果実が十分大きくならないまま熟すということは
糖分等が濃縮する。従って、”より甘い”と感じる。
けだし、Hydroponicsにおいては、通常より導電率を高める事により、理論的には塩土壌状態が作り出せるはずです。
通常とは1.5mS/cm程度です(苺等を除く)。 では、どのぐらい導電率を上げればほどよい塩土壌状態が作れるのかについて、思考中です。
まずは海水を考えてみました。海水浴をすると浸透圧により体液が流出し、しわしわになります。
従って、ここまで上げるのはやりすぎだと考えます。
海水の導電率が(*1)20~50mS/cmとの事です。
また、海水濃度を割り出す式が(*2)PPT=0.0124*μS/cmとの事ですので
試しに30mS/cmと仮定すると、濃度約3.7%程度となり、海水濃度の平均値3.5%に近くなります。
ここからは手探りになります。
ところが、うちのEC計は999μm/cmまでしか計測できないので
探る”手”がまず無いです。
999μS/cmまでだと、通常使用にすら支障をきたします。
養液の水割りで大雑把に値を推測するしかないです。
(*1)https://www.bkb.co.jp/topics/electrical-conductivity-test-flow/ (*2)https://ibottling.com/ja/%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B0%B4%E3%81%AE%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E7%8E%87%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7/
土壌の塩分濃度が濃いため、根からH2O及びイオンを吸収しにくい。
これは、果実肥大期において、与える水分を絞った状態に等しい。
少なくともトマトの場合、1果あたりの総糖量は概ね決まっているため、果実が十分大きくならないまま熟すということは
糖分等が濃縮する。従って、”より甘い”と感じる。
けだし、Hydroponicsにおいては、通常より導電率を高める事により、理論的には塩土壌状態が作り出せるはずです。
通常とは1.5mS/cm程度です(苺等を除く)。 では、どのぐらい導電率を上げればほどよい塩土壌状態が作れるのかについて、思考中です。
まずは海水を考えてみました。海水浴をすると浸透圧により体液が流出し、しわしわになります。
従って、ここまで上げるのはやりすぎだと考えます。
海水の導電率が(*1)20~50mS/cmとの事です。
また、海水濃度を割り出す式が(*2)PPT=0.0124*μS/cmとの事ですので
試しに30mS/cmと仮定すると、濃度約3.7%程度となり、海水濃度の平均値3.5%に近くなります。
ここからは手探りになります。
ところが、うちのEC計は999μm/cmまでしか計測できないので
探る”手”がまず無いです。
999μS/cmまでだと、通常使用にすら支障をきたします。
養液の水割りで大雑把に値を推測するしかないです。
(*1)https://www.bkb.co.jp/topics/electrical-conductivity-test-flow/ (*2)https://ibottling.com/ja/%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B0%B4%E3%81%AE%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E7%8E%87%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7/