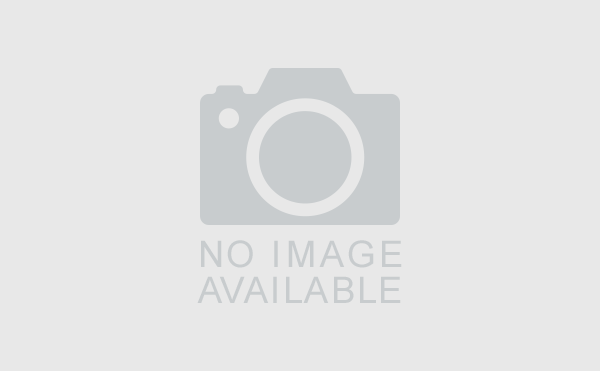徒長 相隣関係
前提として、ここにいう広義の赤色光を610nm~780nmと仮定します。
うち、遠赤色(far red)を700~780とします。
また、フィトクロムの活性型(Pr)が660nmにピーク、不活型(Pfr)が730nmとします。
フィトクロム自体の作用としては、far redの受容によって不活化します。
相隣関係で言うと、隣の植物が自己の背丈より高く、その葉が自己の葉の上に覆いかぶさってるような状態においては、
植物にとって重要なスペクトル(ここではred)を自己より先に取られる(吸収される)ことになり、
従って、自己の葉に届く光のスペクトルはfar redレシオが高くなります。
残り物です。
far redレシオの高まりを受け、隣より背丈を伸ばし、自己の葉を上にしようとする作用が働きます。
いわゆる徒長です。
フィトクロムそのものは不活化するにとどまる(既に新常識が発見されているかもしれませんが)ので、
では徒長、徒な”伸長”はどういった作用機序によるものなのかについては現在のところ100%完璧には説明できません。
植物ホルモンについては未だ謎が多いからです。
ジベレリンの単独作用または他のホルモンとの相互作用によるものの確率が高いですが。
言えるのは、日照権を阻害されて徒長する術を持った種が生き残ってきたという事でしょう。
相隣関係に関しては徒長のみではありません。
うち、遠赤色(far red)を700~780とします。
また、フィトクロムの活性型(Pr)が660nmにピーク、不活型(Pfr)が730nmとします。
フィトクロム自体の作用としては、far redの受容によって不活化します。
相隣関係で言うと、隣の植物が自己の背丈より高く、その葉が自己の葉の上に覆いかぶさってるような状態においては、
植物にとって重要なスペクトル(ここではred)を自己より先に取られる(吸収される)ことになり、
従って、自己の葉に届く光のスペクトルはfar redレシオが高くなります。
残り物です。
far redレシオの高まりを受け、隣より背丈を伸ばし、自己の葉を上にしようとする作用が働きます。
いわゆる徒長です。
フィトクロムそのものは不活化するにとどまる(既に新常識が発見されているかもしれませんが)ので、
では徒長、徒な”伸長”はどういった作用機序によるものなのかについては現在のところ100%完璧には説明できません。
植物ホルモンについては未だ謎が多いからです。
ジベレリンの単独作用または他のホルモンとの相互作用によるものの確率が高いですが。
言えるのは、日照権を阻害されて徒長する術を持った種が生き残ってきたという事でしょう。
相隣関係に関しては徒長のみではありません。